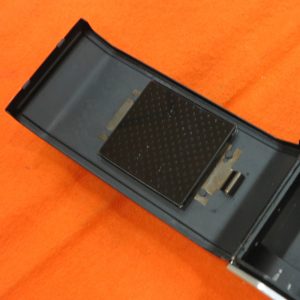一昨日、4月23日に元広島カープ選手の
衣笠祥雄さんが亡くなりました。
私が小学校~中学校くらいまでの
いわゆる「カープ黄金期」の主役でもあった名選手です。
テレビでも球場でもいつも豪快なスイングで
私たちを本当に楽しませてくれました。
「鉄人」の名で呼ばれる衣笠さんですが
印象に残っているのは倒れるくらいの死球を受けた後でも
マウンド方向に「大丈夫だよ」という風に
軽く手を上げて何事もなかったように一塁に走っていく
その姿が鮮明に焼きついています。
心よりご冥福をお祈りいたします。
さてさて
本日は「ヤシカフレックス」のカメラ修理を行っています。
ヤシカフレックスは同じ名前でいろいろなモデルがあり
判別になかなか苦労するモデルです。
修理そのものにはあまり関係ないのではありますが。。。
今回、お預かりしているヤシカフレックスは
フィルター取付部がバヨネットであること
シャッターユニットがコパルMXV(最高速は1/500)
フィルム装填はスタートマーク式、
シャッタースピード、絞り設定がノブ式であること等から
B型後期(新B型)だと思われます。
レンズはヤシコール80mmF3.5です。
セルフコッキングまでは装備されていませんが
非常に使いやすく質感も高いカメラです。
現在、手に入る二眼レフの中でも比較的お求め安いモデルで
これから二眼レフを始めてみる方にも
お勧めできるカメラです。
お預かりしているヤシカフレックスは
シャッターは切れているものの
定番のミラークモリにシャッター羽根にも
少々粘りが見受けられます。
加えてフィルム装填時の巻き止めが効かず
どこまでも巻き上げることができてしまいます。
裏蓋を開けた際にカウンターは「S」マークに戻るのですが
それも随分行き過ぎた場所まで戻ってしまいます。
写真ではカウンターに隠れて見えないのですが
巻き止め部品の先端のツメが見事に折れていました。
「S」マークで止めるピンも歪んで取れかかっています。
何かしらの強い力が加わったようですね。
どちらも中古部品との交換で対処いたします。
部品交換の可能性が高いと思われたので
今回は巻上部の整備から取り掛かりました。
巻上部修理後にシャッターユニット周り、
さらにファインダー部の整備に取り掛かります。
↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。