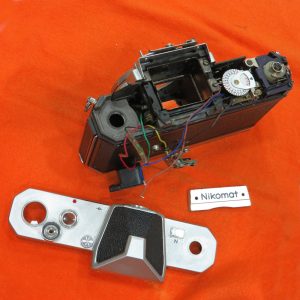今日は9月9日ということで
「重陽の節句(菊の節句」ですね。
奇数は陽の数であり陽数の極である9が重なることから
「重陽(ちょうよう)の節句」と呼ばれ
旧暦では菊が咲く季節であることから「菊の節句」とも呼ばれます。
邪気を払い長寿を願って菊の花を飾ったり
菊の花びらを浮かべた「菊酒」を酌み交わして祝ったりするそうです
お酒は常にあるから菊の花買ってきて花びらを浮かべなければ。。。
重陽の節句はいわゆる「五節句」のひとつなのですが
少々他の節句に比べると地味ですよねぇ
実際の菊の季節が旧暦でもう少し後なのもちょっと残念かな。。。
そういえば子供の頃、10月になると毎年のように
「菊祭り」みたいなのに連れていかれて
菊人形が子供心にちょっと怖かったことをかすかに覚えてるなぁ
たしか5歳くらいの頃だから場所も何も覚えてないけど。。。
あ、昔のアルバム見たらきっとあるような気がします。
こういう忘れかけの記憶を引っ張り出すアイテムとしても
写真は大事ですよねぇ。。。
やはり記録写真こそが最強ですね。。。(笑)
さてさて
本日は「キヤノンF-1」のカメラ修理を行っています。
実は作業自体はあらかた終わっているので
今日はいきなり写真から。。。
今回お預かりしているF-1が元々美品なこともありますが
やはりいつ見てもF-1はカッコ良いですねぇ
またSSC(スーパースペクトラコーティング)の
赤文字FDレンズが似合いますよねぇ
やはり低く構えたペンタ部がポイントなのでしょうね。
ライバルのニコンF2とは正反対のスタイリングですが
どちらも70年代を代表するカメラですね。
お預かりのF-1はやはり長らく整備されていなかった個体と思われ
シャッタ幕軸の油切れのため、何度かシャッターを切っていると
たまに高周波のノイズの混じった嫌なシャッター音がしていました。
高速シャッターの精度も不安定だったのですが
それは油切れというより調速カム周りの偏芯軸のネジが
緩んでしまっていることが原因だったようです。
さらんび低速シャッタ時にはシャッターがたまに開いたままになることが
あったのですがこれも単純にスローガバナの固着とかではなく
シャッタダイヤル裏で使われているチューブが外れ
これがスローガバナまで転がっていき引っかかっていたことが原因でした。
さすがにこういうのは分解してみないと予想はできないですね。
普通に動作するときにはガバナには何の問題もなさそうだったので
ガバナ自体の問題ではないかも。。。とは思っていましたが。。。
もちろん整備後は高速側低速側も申し分ない精度が出ています。
シャッター動作音や巻上感触もお預かり時に比べると
段違いに良くなったと思います。
もともと美品だった外観に中身も追いついて
非常に良い状態のF-1になったと思います。
もう少し様子見をしてから
最終チェックを行い問題なければ完成となります。
ご依頼者様は何度も当店をご利用いただいているお得意様ですが
今回のF-1でも早く撮影を楽しんでいただきたいと思います。
↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。