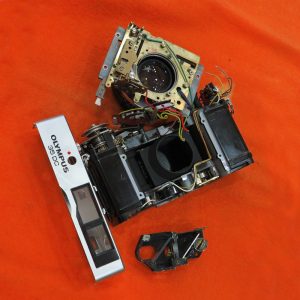今日はあまりピンとくる記念日がなくて
過去の9月25日に起きた出来事を
探っていたのですが。。。
1981年9月25日にフジテレビの「スター千一夜」が
最後の放送をしているのですねぇ
また懐かしい番組ですねぇ。。。
これ聞いてピンとくる方はほぼ間違いなく
私と同世代かそれより上の方ですよねぇ
19時45分から15分間だったかな。。。
さすがにはっきり覚えているほどでもないのですが
芸能人だけでなくスポーツ選手とか
来日した外国人ミュージシャンとか
ジャンルを問わずいろんな方が出ていた記憶があります。
そうそう、夫婦で出演みたいなパターンも多かったような気が。。。
調べてみると1959年3月1日のフジテレビ開局当日から
始まった長寿番組だったのだそうです。
15分とはいえゴールデンタイムにほぼ毎日(月~土)
放送していたのですからすごい・・・というか時代を感じますね(笑)
それよりもすごいのはこうして
「あ、これ調べてみよう」と思ったら何でも出てくる
今のネット環境がすごいですよねぇ。。。
さすがに「スター千一夜」が丸ごと見られるものはなかったですが
オープニングとさわり部分くらいなら動画でも見られるなんて。。。
またこうしてyoutubeとかで探し始めると
仕事にならなくなるのでこの辺で止めておきます(笑)
さてさて
本日は「オリンパス35-S」のカメラ修理を行っています。
オリンパス35シリーズは1948年の「Ⅰ型」から始まり
70年代半ばまでいろいろなモデルを出し続けていた
オリンパスを代表するコンパクトカメラです。
初期の大柄なモデルから70年代のコンパクトなモデルまで
いろいろなものが存在するのですが
「35-S」は1955年に発売開始されたモデルです。
コンパクトカメラというよりもこの時代はまだ
レンズ固定式のレンズシャッター機といったほうが馴染みますね
正直に言ってそれほどコンパクトではありませんし
総金属製なのでそれなりに重いです。
でもこの時代ならではの高い質感を持ち合わせています。
35-S以前のオリンパス35シリーズは
巻上がノブだったのですが35-sでレバー巻上になり
セルフコッキングにもなりました。
フィルムカウンターも自動復元型で
レンジファインダーも搭載されました。
当時の最先端の機能と装備と言ってよいと思います。
シャッターはセイコーシャSLVで最高速は1/500
レンズは生産時期によってF3.5、F2.8、F2、F1.9 と
いろいろなものが搭載されているものが存在します。
今回、お預かりしている35-Sは4.2cmF2が搭載されたものです。
お預かりしている「35-S」ですが。。。
巻上げてレリーズするとシャッター音はするのですが
シャッター羽根はピクリとも動きません。
何回か切っているとたまに普通に開きます。
レンズシャッター機でよくあるシャッター羽根の粘り・固着も
多少はありそうですが
どうもそれだけではなくてシャッター駆動機構部に問題がありそうです。
どちらにしてもシャッター羽根・絞り羽根の清掃は行いますので
シャッターユニットを完全に降ろして整備を行うのですが
ユニット内の汚れや油切れもあり
あちこちで動作不良が起きている状態でした。
きちんと清掃を行い正しく組み立て若干の調整を行います。
それでシャッターの動作のほうは全く問題ない状態になりました。
ファインダー内には撮れないカビ跡もわずかに残りましたが
普通に覗いてみる分には非常にクリアな状態です。
レンズは多少のカビや汚れがありましたが
清掃後は非常にクリアな状態になりました。
これは撮影結果にかなり期待ができる状態だと思います。
外装部品には一部欠落やレンズ前枠の歪みもあったため
中古部品を使って交換を行い
なるべくキレイになるように磨きました。
見た目も動作もかなり良い状態になったと思います。
昨日としては非常にシンプルなカメラですが
それでも先に書いたようにこの時代としては
かなり撮影に便利な機能満載の最新鋭機です。
きちんと使いこなせば
もちろん写りも非常に良いものです。
ご依頼者様にもこの完調となった35-Sで
是非撮影を楽しんでいただければと思います。
↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。