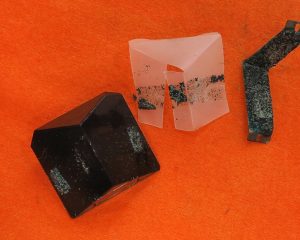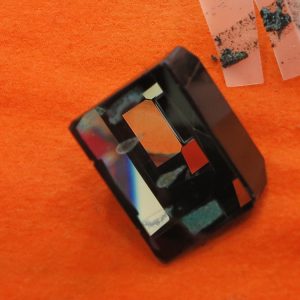今日は「穴子の日」ということですよ。
ウナギほどこってりとはしていませんが
アナゴも負けずに美味しいですよねぇ。。。
お寿司のネタとしても定番で
タレの味が濃いから比較的最後頃にいつも頼ものですが
お腹がふくれかけてても美味しくてぺろりと食べてしまいます。
お寿司もいいですが
「あなご飯」
(かば焼きでうな重のように仕立てたもの)は
瀬戸内名物なので私の生まれ故郷広島では
身近な存在です。
身がほくほくで美味しいのですよねぇ。。。
宮島口の「あなごめし うえの」さんのものが
有名ですね!昔、食べたけど美味しかったなぁ。。。
また機会があったら行きたいです。
そういえば。。。「あなご飯」も美味しいですけど
「鯛めし」も美味しいですよねぇ。。。。
妄想ばかりでお腹すいてきました。。。(笑)
さてさて
本日はいつも大人気の
「オリンパスOM-1」のカメラ修理を行っています。
いつも同じようなことを書いてしまいますが
軽量コンパクトな機械制御シャッター機といえば
やはり一番の名前の挙がるカメラだと思います。
さらにいうと巻上のフィーリングといい
上品なシャッター音と言い
使っていて非常に気持ちの良いカメラでもあります。
軽量コンパクトな一眼レフは
当時だとOM-1の独壇場でしたが
後には同じコンセプトのカメラも出てきて
やはりそれなりに人気モデルとなっています。
それでも「軽量コンパクトな一眼レフ」というと
やはり「OM-1」を思い浮かぶことが多いのは
軽量コンパクトなことだけではなく
そういう使い心地のよさとか造りの良さも
影響しているのでないかと思います。
お預かりしているのは比較的後期のOM-1です。
MD対応なのはもちろんのこと
分解してみるとすぐに気づきますが
内部部品はほぼほぼOM-1Nと同様です。
一通り動作はしているのですが
露出計の指針の振りが鈍く2~3段オーバー指示となってしまいます。
さらに非常に不安定でチェックしていると
何かの拍子に動かなくなってしまいます。
他、巻上が妙に重く
せっかくのOM-1の良い部分がスポいるされてしまっています。
全体的に動きの悪いところも多いので
一通りの分解整備が必要です。
OM-1はそのコンパクトなサイズを実現するために
非常に独特な構造の部分が多く
他の大きなサイズの一眼レフに比べると
やはり華奢な部分も多く
なかなか修理・整備の難易度の高いカメラです。
露出計が不安定な場合は
まずは電池室からの配線を疑い、次にSW部をチェックします。
ただ、今回の場合は電池室からの導通に問題はなく
SW部もトラブルの少ない「1N」と同様の構造のため
それが原因でもありません。
色々調べているとどうやら露出計本体のアースが接触不良のようです。
「1N」のタイプに露出計周りの構造が変更された際に
露出計のアースの位置や構造も変更されているのですが
この構造になってからアース不良を見かけることが多いような気がします、」
少し前にも同様の症状を見た気が。。。(汗)
ある程度、原因が絞り込まれたので
巻上部やシャッター周りの整備を先に行います、
その後、露出計周りの整備調整を行い完成へと向かいます。
↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。