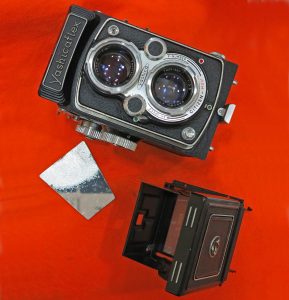今日は「ケーキの日」だそうですよ!
甘いもの大好きな私ですから
もちろんケーキも大好物です!
しかしながら調子に乗って食べると
いろいろ問題が。。。(汗)
でも「ケーキの日」なら少しぐらいいいですよね!
仕事帰りにどこかでケーキ買って帰りましょう~
さてさて
今日はミノルタXEのカメラ修理を行っています。
巻上の滑らかさで有名なカメラですね。
巻上だけでなく全体の使用感が素晴らしいカメラです。
私も個人的に何台か持っていますが
今でも根強いファンの多いカメラですね。
発売は1974年。
Xシリーズとしては前年のX-1に続いて
2機種目のモデルにあたります。
ライカR3のベースになったことでも有名なカメラです。
比較的初期の電子制御シャッター機ということもあり
多少トラブルの多いカメラでもあります。
しかしながら最大の弱点は電子制御部分ではなく
現存するXEの8割が発症していると思われる
プリズム腐食だと思います。
酷いものになるとファインダー視野内下部半分近くが
真っ黒になってとても使える状態ではなくなります。
今回、お預かりしているXEも下1/3に
うっすら黒い帯が見えています。
プリズムを外してみると、過去に腐食に対処したらしく
腐食部分にミラーテープが貼ってありました。
だから腐食部分がモヤモヤした見え方になっていたのですね。
しかしこれでは腐食部分ではピント合わせもできません。
今回は中古良品のプリズムを移植して対応します。
XEといえば露出計のトラブルも多いのですが
今回はパッと見た感じでは1.5段アンダー、
調整で何とかなるかと思ったのですが
絞りを動かしていくとあるポイントで針が完全に振り切ります。
これも巻き戻しクランク下の摺動抵抗がダメなようです。
ここも交換で対応します。
シャッター制御自体は何とか動いているようなので
まずはそこの点検整備から取り掛かります。
電子制御機は突然壊れることも多い上、
XEはやたらと接点の多いカメラで
そこをしっかりメンテナンスしてやらないといけません。
これから本格的に分解を進めて取り掛かります。
↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。