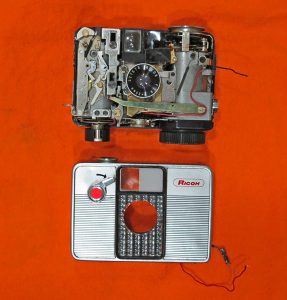今日は「愛と希望と勇気の日」らしいですよ。
南極観測隊のカラフト犬、タロとジロに由来した日なんですね。
直接関係無いですが
子供の頃に「炎の犬」ってドラマがあって毎週見ていたなぁ。。。
主題歌は杉村尚美さんの「サンセット・メモリー」
同じような時期に「黄金の犬」ってドラマもあってこれも毎週見てました(笑)
さてさて
本日は「ミノルタALS」のカメラ修理を行っています。
隠れた名機である「ミノルチナS」の後継モデルで
受光素子がセレン光電池からCDSに変更されたモデルです。
この時代としては非常にコンパクトなレンジファインダー機で
スタイリングも何とも秀逸です。
巻上げやシャッター音等の操作感もミノルタらしくとても良い感じです。
今回、お預かりしている個体は
鏡胴が妙にグラグラしています。
レンズボード裏で鏡胴全体を締めているリングが
緩いのではないかと思われます。
途中まで分解していて思ったのですが
それ以外にも全体的にネジが緩い印象です。
固着してガチガチに外れないのも困りますが
ガタつくほど緩いのも困りますね。
露出計は随分オーバー傾向にありますので
シャッターユニット、レンズ清掃等々、各部点検整備一式と一緒に
調整いたします。
40mmF1.8の大口径レンズがついて距離計もあって
適度にコンパクト。改めてALSの良さを再確認しました。
↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。