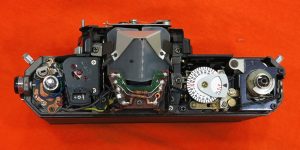今日は「音の日」だそうですよ。
1877年のこの日にエジソンが自ら発明した蓄音機で
録音・再生に成功したとのことです。
気がつけば最近、レコード、CD、買ってないなぁ。。。
最近のCDを欲しいとはあまり思いませんが
ひとたび中古レコード屋さんに足を踏み入れれば
おそらく4、5枚はアルバムを衝動買いする自信はあります(笑)
新宿に行くたびに「レコード屋さん寄ろうかな。。。」と
いつも頭の片隅には思っているのですが。。。
時間のあるときにゆっくり見たいですねぇ。。。
さてさて
本日は「コニカFTA」のカメラ修理を行っています。
1968年発売のカメラです。
コニカというとやはりレンズ一体型の
コンパクトカメラのイメージが強いですが
1960年のコニカFから一眼レフも生産しています。
今回のFTAは1968年の発売です。
ARレンズとの組み合わせでシャッタースピード優先オートが使えます。
コンパクトカメラで当時よく採用されていた
露出計の針を挟み込むタイプのオート露出です。
シャッターは機械式制御のコパルスクエアです。
露出計指針挟み込みの構造上の理由もあるとは思いますが
シャッターレリーズがちょっと深め(長め)のカメラです。
おもしろいのは装着するレンズによって
測光範囲が微妙に変化します。
広角レンズでは中央部部分測光、
標準レンズでは中央重点測光
望遠レンズでは平均測光となります。
前期型と後期型が存在し
背面にON/OFFスイッチがあるものが前期型です。
お預かりしているFTAはまず露出計が動きません。
それもそのはずで電池室を見ると
マイナス側の端子が外れて中に入り込んでしまっているようです。
マイナス端子はカシメて電池室に取り付けられているのですが
ここが少し構造的にも弱いようで
電池室のプラスチックが劣化してくると
外れてしまうものが多いようです。
もちろん電池を入れっぱなしで腐食させてしまうと
まず間違いなくここの端子も脱落します。
加えてFTAに多いのは接眼レンズのクモリです。
張り合わせレンズの内側が曇っている場合が多く
交換するしか方法のない場合が多いです。
。。。とはいえ、中古でクモリのない接眼レンズが
なかなか見つからないのが実情です。
当店ではできる限りの清掃で対応しています。
今回のFTAもかなり激しく曇っていたのですが
張り合わせ内側でなく内側表面のクモリだったので
今回は清掃で問題ないレベルまで
キレイにすることができました。
一通りの整備を行って少し様子見の状態です。
露出計は当然、普通に作動するようになり
オート露出の精度も含め申し分ない状態になりました。
シャッターはもともとそれほど悪い数値ではありませんでしたが
やはり羽根汚れのため先幕・後幕のバランスが
少し崩れている状態でしたが
こちらも問題ないレベルまで改善しています。
写りの評価が非常に高いヘキサノンレンズを
存分に楽しんでいただけれる状態になったと思います。
↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。