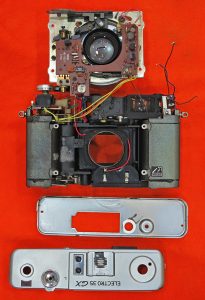今日は「霜降」ですね。
露が冷気によって霜になり始めるころ。。。ということですが
まだまだ都心では昼間は充分暖かいし
霜にはちょっと早いですね。でも朝晩は確かに涼しいというより
寒くなってきましたね。
平地に紅葉前線が降りてくるのももうすぐです。
さてさて
本日は「ニコマートFTN」のカメラ修理を行っています。
ニコンの普及ブランドとして名づけられた「ニコマートシリーズ」ですが
この「FTN」が一番見かけることが多いのではないでしょうか。。。
普及機クラスとはいえ、この時代のカメラは高級品ですから
非常にしっかりと造りこまれています。
今回お預かりした個体も
モルトはボロボロですがしっかり作動しています。
ただし、羽根の汚れからか
後幕の動きが少々悪く、高速シャッターでは露光ムラが出ているようです。
他はニコマートFTNでは定番の露出計トラブルです。
今回は2段ほどアンダー目に指示してしまうようです。
たとえネガ使用だったとしても2段アンダーだと
写真はさすがに暗くなってしまいますね。
ニコマートFTNの露出計のトラブルはいくつかパターンがあって
基盤のハンダ付けが劣化
基盤内の抵抗が劣化してスカスカになっている
CDSそのものの劣化、マウント基部にある抵抗が劣化、等々がございます。
今回もこのどれかだと思われます。
搭載されるコパススクエアシャッターは非常に堅牢で
致命的な故障を見かけることがほとんどありません。
(ショック品や水没品を除く)
とはいえ、羽根の汚れやユニット内の油切れも疑われるので
これから分解を進めシャッターユニットの整備から行います。
もちろん、その後で露出計の修理も行います。
↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。