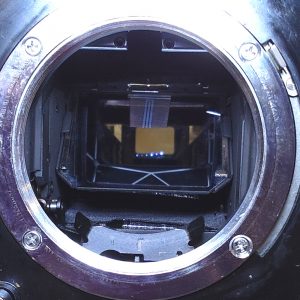今日は「かきフライの日」だそうですよ。
11月はかきが美味しくなる時期で
21日は「フ(2)ライ(1)」と読む語呂合わせからだそうです。
かきフライに限らず本格的な真牡蠣の季節の到来ですが
私の地元でもある瀬戸内の真牡蠣が
今年は壊滅的な状況のようです。
毎年この時期になると殻付きの生食用真牡蠣を
取り寄せるのですが今年はそれも無理そうです。
牡蠣が卵から収穫まで3年ほどかかるらしいのですが
今年はもうしかたないとしても
来年以降は大丈夫なのか非常に心配です。
来年の今頃は美味しい牡蠣を食べられればいいのですが…
しかし天候や気候に大きく左右される
生産者の方々は本当に大変ですね…
さてさて
本日は「キヤノンAE-1プログラム」(以下AE-1P)の
カメラ修理を行っています。
1981年発売のカメラです。
当店で扱うキヤノン機としては最新のモデルです。
といっても44年前のモデルです。
機械的な駆動構造は「Aシリーズ」一号機である
「AE-1」のものを引き継いでいます。
ただこの5年間の間に電子制御技術は大きく進化を遂げ
制御回路関連はもう全くの別物となっています。
初代AE-1ではまだ糸連動が残っていた部分もあるのですが
AE-1Pではからくり的制御はほぼなくなり
電気信号で内部伝達が行われています。
露出計も指針式ではなくLEDで絞り値が表示されるようになり
随分と現代的になりました。
そのファインダーもAE-1に比べれば
数段明るくキレの良いものとなり
A-1でもまだ残っていたコンデンサレンズの配置もなくなりました。
ファインダースクリーンも
下から簡単に取り外せるようになっています。
機能的な面で目立つのは露出モードにプログラムオートが
追加になったことぐらいなのですが
それ以上に全体的にブラッシュアップされ
初代AE-1とは明らかに時代の違いを感じます。
外観も随分と洗練されたデザインになりました。
お預かりしている「AE-1P」は
まず定番の「シャッター鳴き」です。
シャッターを切ってミラーが駆動する際に起こる異音で
「Aシリーズ」全機種の定番トラブルです。
制御面ではモデルごとに大きく進化していますが
機械的な駆動部のベースはすべて初代AE-1なので
すべての「Aシリーズ」のカメラで起こる症状です。
異音が出るということはミラーの動きは当然ながら
悪くなっており、症状が進むと明らかに見た目でも
ミラーの動きがゆっくりになっているのがわかるようになります。
そして最終的にはミラーが動けなくなって
シャッターが切れなくなります。
定番のトラブルということもあって
原因箇所はわかっているので
分解整備時に対処を行います。
加えて露出計・オート制御がずいぶんオーバー目に
ズレてしまっていることと
レンズの絞りをボディ側から制御するレバーの動きが悪く
オート制御が不安定なようです。
これもありがちなトラブルで原因もわかっていますので
原因箇所の修理整備を行っていきます。
まだ取り掛かったばかりの状態です。
これから本格的に分解整備を行っていきます。
上カバー開けた時点での光景がAE-1とはまったく別世界です。
それでもこの類のカメラとしてはかなり整備性が良い方です。
この季節になってくると特にですが
このタイプのカメラを扱う際には
静電気を気にしなければなりません。
帯電した指なんかでうっかり基盤に触ると
その瞬間に修理不能な状態になってしまう可能性があります。
細心の注意で整備に取り掛かっていきます。
↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。