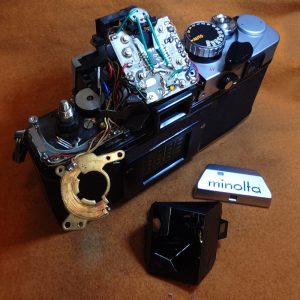今日は「人口調査記念日」だそうですよ。
1872(明治5)年のこの日に
明治政府による日本初の全国戸籍調査が行われたそうです。
当時の人口は男1679万6158人
女1631万4667人で合計3311万825人でした。
2015(平成27)年の国勢調査による日本の総人口は
1億2709万4745人で、9000万人以上増えたことになります。
最新の調査では現在の人口は1億2359万人だそうです。
いずれにしても150年ほどでこんなに増えたのですね。
これからは人口は減少傾向に推移するのでしょうが
これから100年後あたりはどんな世の中になっているのでしょうね。
もちろんそれを見ることは無理ですが…(笑
さてさて
本日は「コニカFP」のカメラ修理を行っています。
コニカというとどちらかといえば
レンズ一体型のレンジファインダー機や
C35に代表されるコンパクトカメラのイメージが強いですが
一眼レフにも早い時期から参入しています。
1960年にファインダー交換式の最高級カメラ「コニカF」の
発売に始まり立て続けに一眼レフをリリースしています。
今回の「FP」は1962年発売のカメラで
それまでの中級機「FS」をベースに
CdS使用の外付け露出計を装着できるようになったものです。
レンズマウントはコニカマウントで
後のオートレックス登場以降に採用された
コニカⅡマウント(ARマウント)との互換性はありません。
ボディからの絞り込み連動が鏡胴外側に露出しているところが
特徴的なレンズマウントです。
「コニカF」以降に登場したコニカ中級機は
「FS]「FP」「FM」と存在しますが
いずれも基本的な構造は共通で
シャッターはその後、いろいろなカメラで採用される
コパルスクエア(当時の呼称はコパルスケヤ)シャッターです。
お預かりしている「FP」は一通りは動作しているものの
多少巻上に油切れの兆候が見られます。
シャッター羽根にも汚れがあると思われ
構想シャッターが多少不安定です。
そしてファインダーが妙に曇っています。
プリズムが汚れていることもありますが
おそらく接眼レンズ内側が曇っているものと思われます。
接眼レンズの変質の場合は清掃では対処できませんが
できる限りの清掃である程度はクリアになると思われます。
FS,FP、FMあたりの接眼レンズがよく曇るのは
上の画像にも写っていますが
接眼レンズとプリズムの間にあたる部分に
モルトが貼られており
そのモルトが加水分解してしまうことも
影響していると思われます。
いずれにしてもコニカの一眼レフは
初期の「F系」のみならず
後のオートレックス系(FTAやオートレックスT3も含む)も
接眼レンズが良く曇るのです。
そしてそれが清掃では改善できない場合も多いです。
これからファインダーも含め
シャッター、巻上、ミラー駆動部と
各部の分解整備を行っていきます。
↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。