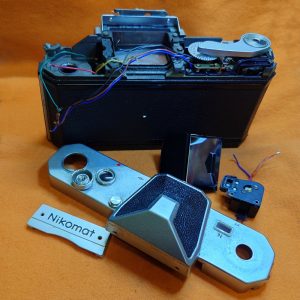今日はわかりやすく「119番の日」ですね。
これから空気が乾燥する季節になり
火事が起きやすい時期になっていきます。
火の管理には本当に気をつけなくてはいけませんね。
ちなみに簡単に調べてみたところ
2023年のデータで火事の最も多い月は3月だったようです。
以降、1月、2月、12月と続きます。
やはり冬から春にかけてが多いのですね。
救急も含めてあまり119番に
お世話になることにないようにしたいものです。
ところで、火災報知の電話サービスが
1926(大正15)年に導入された際の番号は
「112番」だったそうです。
当時はダイヤル式の黒電話で一刻を争う緊急のために
ダイヤルを回す時間の短い番号として指定されたのですが
意外とかけ間違いが多かったそうです。
そこで、翌年の1927(昭和2)年にかけ間違い防止と
最後にダイヤルを回す時間が長い「9」を回すことで
落ち着いて話ができるためという理由で
現在の「119番」になったと言われています。
警察への緊急通報の「110番」も同様の理由とされているようです。
うちにはまだダイヤル式の電話が実働していますが
そんな理由があったのですね。
さてさて
本日は「キヤノンL3」のカメラ修理を行っています。
1957年発売のカメラです。
当時のキャノンお得意のフォーカルプレーンシャッタの
レンジファインダー機です。
必要最小限の機能だけでシンプルに仕上げたカメラです。
最高SSは1/500となります。
お家芸の変倍ファインダーはしっかり装備されています。
奇をてらったところのない端正な外観がなんとも魅力的です。
巻き戻しノブの横にありレバーを手前に引くと
フラットに格納されているノブがぴょこんと飛び出してきて
巻き戻しが可能になります。
ちょっとしたギミックですがこれも楽しいですね。
お預かりしている「L3」は
まず距離計二重像が大きくズレています。
縦ずれも少しありますが
水平方向へのズレが大きくこの距離計で合わせると
ピンぼけを多発しそうです。
加えてやはり各駆動部は動きの重い部分があり
高速シャッターの精度は出ていません。
巻上機構も含めて幕軸等の清掃整備が必要な状況です。
お馴染みのもなか構造で整備性は非常に良好です。
この状態でまずは各駆動部の動きを確認してから
本格的な分解整備へと取り掛かります。
巻上を確認しながらゆっくり動かしから
シャッターを切ると各部が非常に精度高く
動いているのがよくわかります。
この時代のキヤノンのレンジファインダー機らしく
非常にしっかりと作りこまれたカメラです。
↓ をクリックすると「東京フィルムカメラ修理工房」のホームに戻ります。